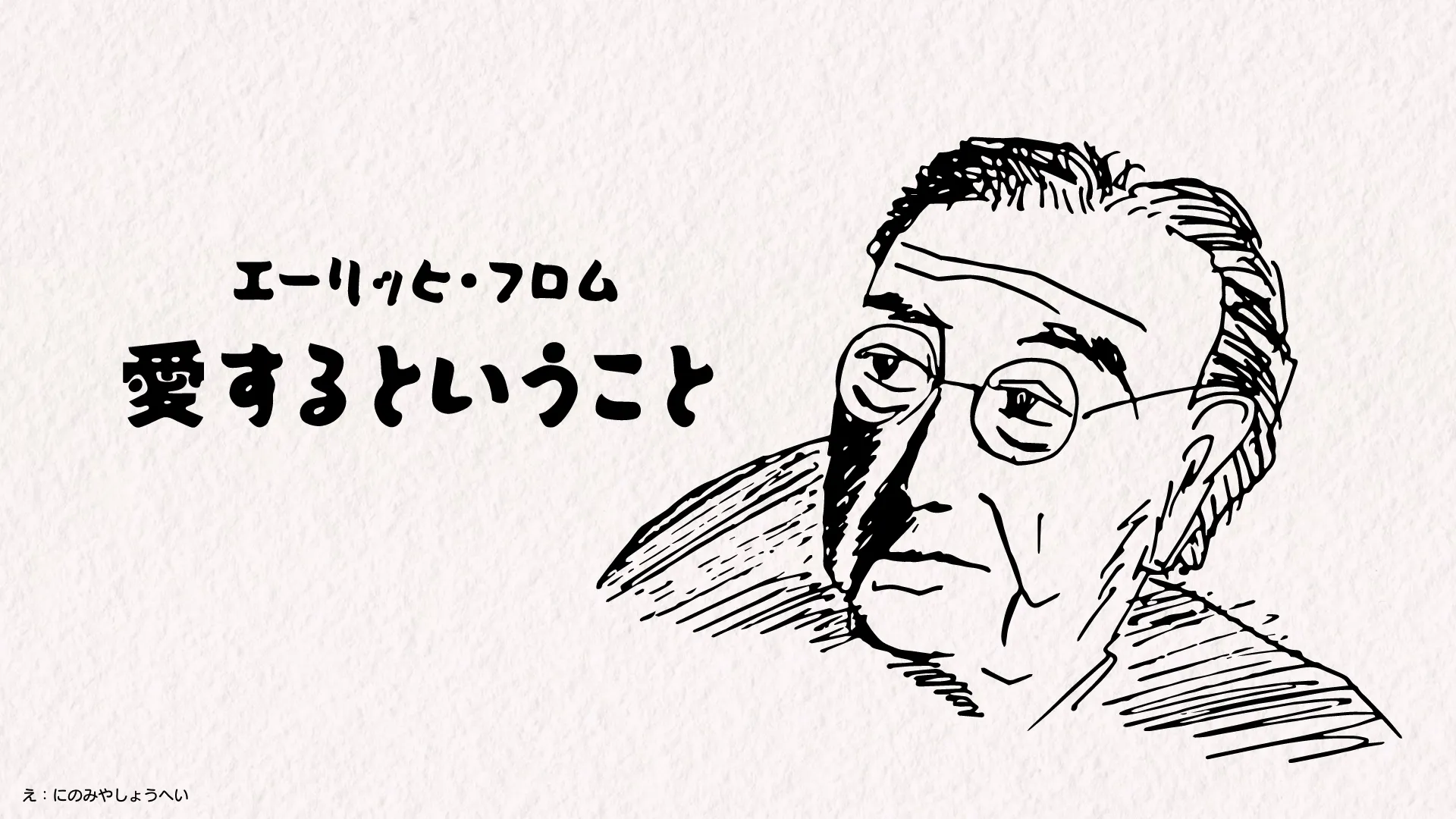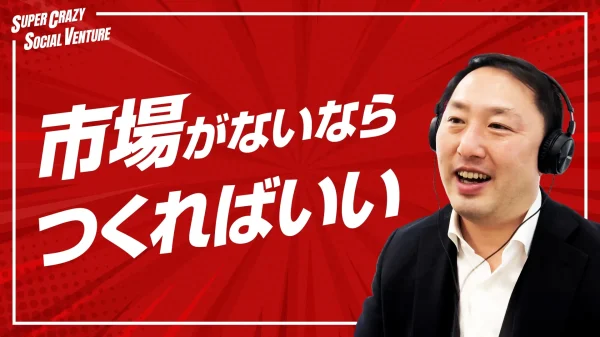#40 哲学書から経営へ~経営者に必要な「愛する力」とは
アーラリンクが幹部教育の一環で行っている「ブックリーディング」。そこで出会った哲学書『愛するということ』が、リーダーとしての姿勢や人への向き合い方に大きな気づきをもたらしました。愛は技術であり、訓練できる。経営における“愛する力”を語ります。
- 目次
- ブックリーディング
- 哲学書『愛するということ』との出会い
- 秀吉のような人になりたい
- 愛を実践するための4つの技術
- 「シャッターを下ろさない」という誓い
- 公平性と経済合理性の間で
- 母性的な愛と父性的な愛
- 本を通じた気づきと家庭でのエピソード
- マーケティングの定義をめぐる議論
- 経営者に求められる「愛する力」
ブックリーディング
私はここ最近、幹部教育の一環としてブックリーディングを続けています。単に本を読むだけでなく、学んだことを皆で共有し、自分自身のリーダーシップに照らして考える場になっているんです。もっと頻度を増やしてもいいなぁと思うくらい、手応えを感じています。
哲学書『愛するということ』との出会い
最近のブックリーディングで選書したのは、エーリッヒ・フロムの『愛するということ』です。
冒頭に「愛は技術である」と書かれていて、とても衝撃を受けました。対象がこうだから愛するのではなく、自分が「愛する」と決めて主体的に行うものだという考え方です。
リーダーにとって、人に対して愛を持って接することは欠かせない。そう改めて感じました。
秀吉のような人になりたい
自分は「織田信長タイプ」だと思います。ただ、上司としては豊臣秀吉的な要素も必要なのではないかと感じています。
秀吉のように人に関心を寄せ、気に入られる存在でありたい。けれど、自分はどうしてもその部分が苦手で、課題意識を持っていました。
そこで「愛するということ」を読むことで、愛は技術であり、訓練で身につけられるものだと理解できたのです。
愛を実践するための4つの技術
フロムは「相手を知る」「尊重する」「配慮する」「責任を持つ」という4つの技術を挙げています。これらを実践することで、誰かを愛することができる。このシンプルな枠組みは非常に腑に落ちました。これを自分がどう実践できるか、考えるきっかけになりました。
「シャッターを下ろさない」という誓い
私にとって大きな学びは「自分からシャッターを下ろさない」と決めたことです。
理解できない相手に出会うと、つい諦めてしまいがちです。でも、それではダメだと思ったんです。
理解できないからといって切り捨てるのではなく、理解しようと関心を持ち続ける。これは自分自身の決意になりました。
公平性と経済合理性の間で
もちろん現実には時間が有限です。変化が早い人にエネルギーを注ぐのは合理的です。しかし、なかなか変わらない人に対しても、向き合い続けることが「愛情」だと思うようになりました。
「公平じゃないと愛せていないのでは」と思い込み苦しんでいましたが、それは違うと気づけたのも大きな収穫です。
母性的な愛と父性的な愛
私は条件付きで愛する「父性的な愛」の傾向が強いと思っています。けれど、誰にでも無条件で注ぐ「母性的な愛」も必要だと感じました。
たとえば「ごちそうさまでした。美味しかったです」と一言添える。エレベーターで人が降りるのを待つ。そんな日常の小さな行為も、母性的な愛を育む訓練になると考えています。
本を通じた気づきと家庭でのエピソード
面白いことに、この本を読んでいたら妻の本棚にも同じ本がありました。別々に買っていたんです。
私は幹部教育の一環で、妻は妻で興味を持って。偶然の一致ですが、笑い話のようなエピソードになりました。
偶然ですが、まるで「浮気を疑われた」みたいな笑い話になりました。
経営者に求められる「愛する力」
最終的に感じたのは、経営者や上司にとって「愛する力」は不可欠だということです。愛情の量が多い方が、人間関係も組織も必ずうまくいく。これは経済合理性の面から見ても得なのです。
だからこそ私は、訓練を重ねて愛情を持ち続ける人間になりたいと強く思っています。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。