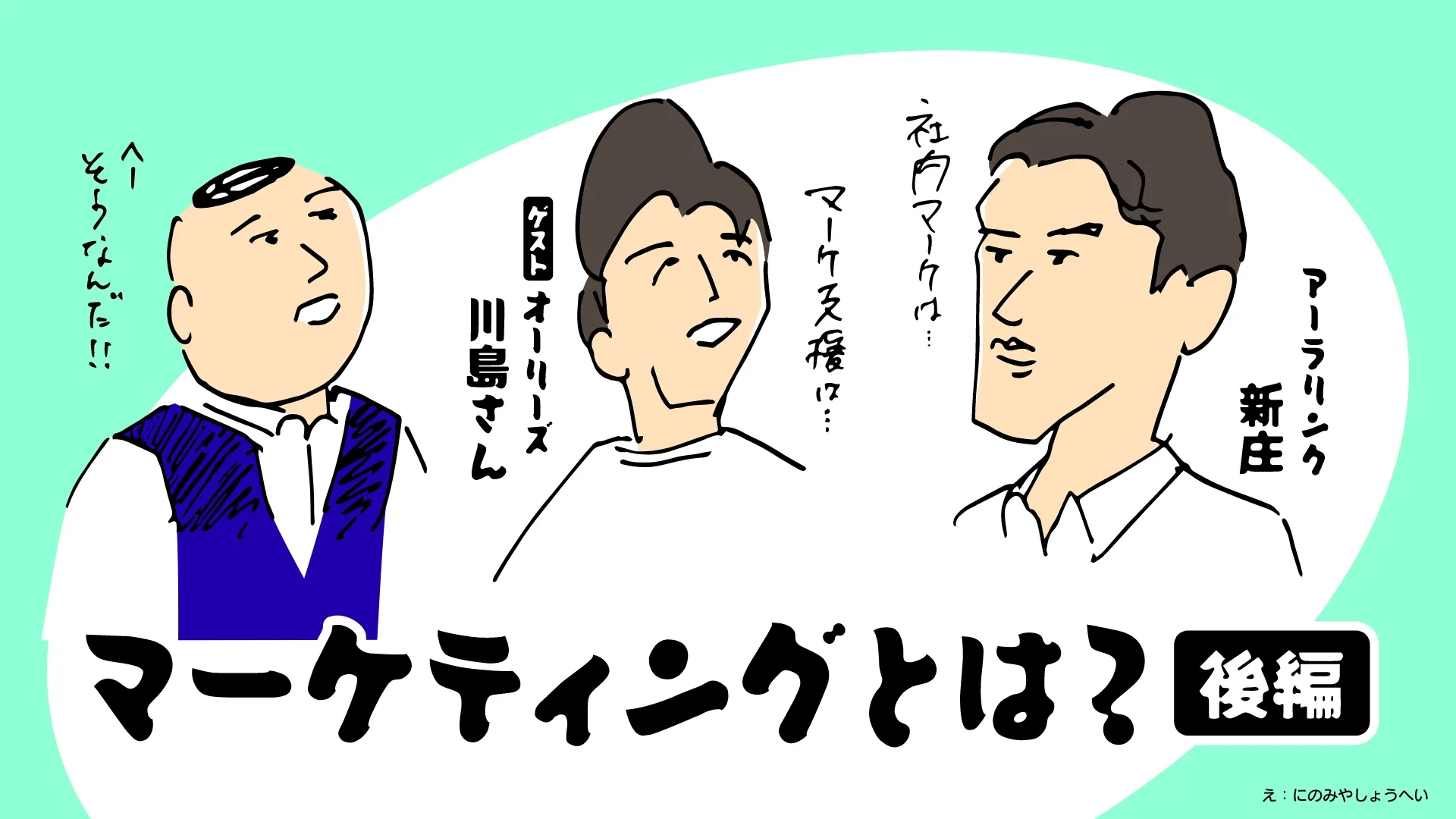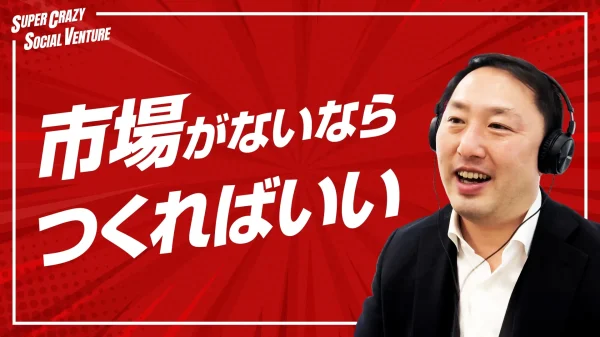#38 【後編】事業会社と支援会社のマーケ育成論~「手に職」と総合力、マーケティング人材の未来(ゲスト:オーリーズ 川島さん&アーラリンク 新庄)
事業会社と支援会社では、マーケティング人材の育成にどんな違いがあるのか。本編では、アーラリンク高橋・新庄と、オーリーズ川島が本音で議論します。OJTによる未経験者育成、顧客満足度を軸にした評価、人がプロダクトになる支援会社の強み、そして「マーケティング=経営」という視点まで、マーケティングの奥深さを体感できる回です。
- 目次
- 事業会社のマーケティング育成の難しさ
- オーリーズさんの育成方針
- 未経験採用とOJTの現場感
- オペレーションに必要な論理性
- コンサルタントとしての判断と成長スピード
- 「人がプロダクト」という考え方
- 顧客満足度を基点にした評価制度
- 事業会社と支援会社の違い
- マーケティングの定義をめぐる議論
- 「手に職」志向への違和感
- 非分業型支援会社の特徴
- マーケティング=経営という視点
- エンディング
事業会社のマーケティング育成の難しさ
高橋:先に川島さんに聞きたくて。事業会社のマーケの育成って本当に難しいんですよ。
新庄さんがプロジェクトを明確に作って、それをやってもらって、だんだん道筋を荒くしていく感じでやっているんですけど、結局、僕らの感覚だと谷底に落として自力で上がってくるのを、最初は浅い谷からだんだん深くして、生存競争をしている感じ。
最後は深い谷に落ちても上がってこれた人はポテンシャルがあるからそういう人を頑張らせる。
でもこれって教育なんだろうか、って結構思うんです。
オーリーズさんのような支援会社では、マーケ人材の育成をどう考えているのか、すごく聞いてみたかったんですよね。
オーリーズさんの育成方針
川島:これは非常に難しくて、永遠のテーマだと思っています。
絶対的な正解はないですね。基本的にはOJT形式が近いと思います。
もちろん知識として書籍や体系化されたものをインプットしますし、オンボーディングもやります。
ただ育成に関しては正解がない世界なので、常に探し続けて改善し続けることが仕事のど真ん中です。
それを繰り返して経験値を積み、成長していく。そこが基本方針ですね。
私たちにとってはプロダクトそのものが「人」ですから、コンサルタント一人ひとりの力量がプロダクトです。
だから育成はOJT、勉強会、あらゆる手を尽くしています。
未経験採用とOJTの現場感
高橋:オーリーズさんは新卒採用ってやってるんですか?
川島:新卒は一切やっていないですね。7割くらいが未経験で、現場で育てていきます。
オペレーションに必要な論理性
高橋:OJTや勉強会だと、正解があるオペレーション的な仕事は少ないんですか?
川島:最初はオペレーションから入ります。オペレーションほど具体性が高く、正解らしきものもある。
論理的に正しいとか合理的といった判断が求められる場面です。そこから中小度が上がると複合的な要素が絡むので、求められるスキルも変わってきます。
高橋:僕はオペレーションって「決められた手順をやるだけ」だと思っていました。でも支援会社のオペレーションは論理性や合理性が問われるんですね。
川島:そうですね。たとえばリスティング広告の成果が高いキーワードに寄せていく判断。これは誰でも分かる話ですが、そこから複雑な要素が絡んでいきます。だからコンサルタントの業務は判断が前提にあります。
コンサルタントとしての判断と成長スピード
高橋:成果の良し悪しで入札を変えるような業務はオペレーションですよね。
川島:そうですね。オペレーション色が強い仕事です。
高橋:でもそれも自分なりに判断して寄せたり外したり、お客様のアカウントを使って進めていくんですね。突破できる人とできない人は出ますか?
川島:基本的には突破できます。ただスピードの早さに差が出ますね。
「人がプロダクト」という考え方
新庄:川島さんの「人がプロダクト」という考え方、すごいなと思いました。我々は商品そのものがプロダクトですが、支援会社は人がプロダクトになる。その違いが大きいなと。
高橋:やっぱりオーリーズさんだと、自己成長意欲が活躍する人の条件なんですか?
川島:間違いなくそうです。評価にも直結しますし、能力評価がそのまま評価です。結果だけでなく、プロセスや顧客満足度を重視しています。
顧客満足度を基点にした評価制度
高橋:確か顧客満足度サーベイをされていますよね。
川島:はい。私たちはお客様の満足を起点に組織を運営しています。結果だけでなく、いかに高い満足度を得られているかをKPIにしています。
高橋:事業会社の我々は商品をもっと広めるとか、お客様を良くする目的に従事している感覚が強いです。そのためには商品や価値観に共感していることが必要ですね。
新庄:そうですね。会社の価値観、そこからくる商品の思いは働く上で共感していないといけない。それを提供するお客様の境遇の理解、共感もとても大切だと改めて感じました。
事業会社と支援会社の違い
高橋:マーケターを採用するとなると、やっぱり支援会社の方が取りやすい印象があるんですよ。24時間365日、他社も含めてマーケティングに取り組んでいるわけですし。
先ほど川島さんが「自分が商品だ」とおっしゃっていましたが、ああいう言葉を聞くと僕も込み上げてくるものがあるんですよね。
だから、マーケをやるなら支援会社で経験を積む方が「ザ・マーケター」として活躍できるのかなと思う部分があって、正直うらやましいと感じます。
逆に川島さんの立場からすると、「いやいや、事業会社のマーケターの方が実は羨ましい」と思う側面があるのか、それとも「いや、支援会社の方がやっぱり楽しい」と感じるのか。そのあたりをちょっと聞いてみたいなと思いました。
川島:採用の面では本当にケースバイケースですね。
そもそも「マーケティング」という言葉の定義自体が人によってかなり違います。マーケティングのど真ん中でやっている人からすると、広告運用はマーケティングではなく、その一部でしかないという考え方になります。私自身もその解釈が正しいと思っています。
ですので、「マーケティングをやりたい」となると、それは事業会社でなければできないことだと考えています。
マーケティングの定義をめぐる議論
高橋:マーケティングは事業会社じゃないとできない、これは大きな視点ですね。
川島:はい。私たちは外部支援業者ですから、線引きは必ずあります。
高橋:そうすると採用や働くという面で見ると、僕は支援会社の方が特化していてすごいなと思うんですが、川島さんからすると事業会社は「マーケティングしていていいな」と思う部分があるということですか?
川島:はい、そうです。これは今の仕事に不満があるとかそういう話ではなく、本当にフラットに見て、事業会社は楽しそうだなと感じますし、興味を引かれます。
実際に代理店から事業会社に転職するキャリアパスもとても多いです。
そこで一つの領域を深めていた人が、事業会社に行けば全部を見なければならない。そうなるとキャリアの広がりも大きいですし、自分の得意領域を突き詰めたいなら支援会社で特化する方が合っています。
私は両方経験してみたいという考えがあるので、事業会社は楽しそうだし、やってみたいなと思う気持ちは日頃からありますね
高橋:そう思ってもらえるのは嬉しいです。僕自身、全然見えていなかった視点でした。
新庄:ドラッカーも「マーケティングは販売を不要にすること」と定義しています。世の中では、CMやWeb広告をマーケティングだと捉える人が多いですが、もっと広い意味で考えると、マーケティングを本当にやっているのは事業会社だというのは納得できます。
支援会社は「手に職がつく」イメージが強く、それが支援会社のマーケティングっぽいなと思いました。一方で事業会社は、何をやっているのか一見分かりにくいですが、総合力がつく。そんなイメージを持ちました。
高橋:クリティカルシンキングが大事だとよく新庄とも話します。事業会社は自由度が高い分、適切に判断する力が必要になりますよね。
「手に職」志向への違和感
高橋:僕らが採用面接をすると「手に職をつけたい」という志望動機が多いんです。でも正直モヤモヤするんですよね。僕らは総合能力を重視しているから、違和感があるんです。
川島:支援会社でも「専門領域で尖りたい」という人は多いです。国内の多くの会社は分業体制なので、Google広告だけ、Meta広告だけ、といった狭い領域で専門化されます。
ただオーリーズは非分業で、フロントから運用まで全部担当します。その点に魅力を感じて入社する人も多いですね。
非分業型支援会社の特徴
高橋:オーリーズさんはクライアント数を絞って、真の課題に向き合うスタイルですよね。だから扱えるチャネルや分野が広い。
川島:そうです。広告チャネルを総合的に理解した上で提案できる体制にしています。国内では非分業型は数えるほどしかありません。
だから「マーケティングに関わる」といっても、どの範囲を指すかは会社ごとにかなり違いますね。
高橋:確かに。「SNS広告を回すこと」をマーケティングと呼ぶかどうかでも解釈が分かれますよね。
川島:そうですね。その議論は常にあります。
マーケティング=経営という視点
新庄:マーケティングの定義は人によって違いますね。「広い意味でのマーケティングをどうやって行くのか」をずっと考えたいと思っているし、それを今日話せたのはすごくよかったです。
川島:そうですね。一昔前だと、リサーチ部門の仕事だと捉える人のイメージもありつつ、経営そのものと考える人もいて、真逆だったりしますよね。
高橋:僕らは「マーケティング=経営」という意識でいます。マーケティングを頑張らないと社員に給料を払えない。それは経営そのものですから。
マーケティングという言葉の定義をお互いが間違えずに共有することが大事だと思います。
エンディング
高橋:いやあ、勉強になりました。
新庄:僕もです。
川島:とても興味深く、楽しいテーマでした。
高橋:スーパークレイジーソーシャルベンチャー、また次回をお楽しみに。ありがとうございました。
新庄・川島:ありがとうございました。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。