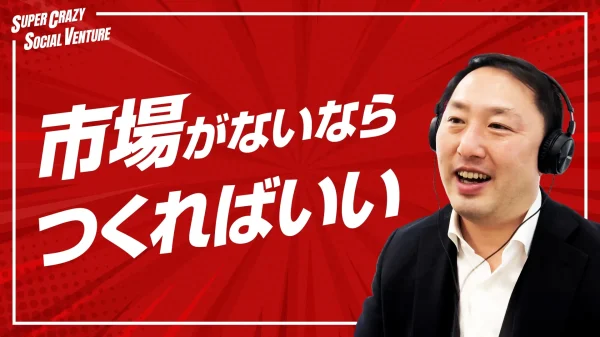#37 【前編】マーケティングの解像度を上げる~事業会社と支援会社のマーケティングの違い(ゲスト:オーリーズ 川島さん&アーラリンク 新庄)
「なんかモヤモヤすんなと思ってた」マーケティングに対する”キラキラ”のイメージ、その裏側にある“覚悟と気合”のリアルとは?今回は初のゲスト回!事業会社アーラリンクと支援会社オーリーズ、それぞれのマーケターが本音で語り合う対談の前編。やり抜く気合、自由と責任の重み、活躍できる人の共通点…。マーケティングで生きるとはどういうことか?マーケティングの解像度を上げたい人は必聴の内容です。
- 目次
- オープニング
- テーマ「マーケティングの仕事の解像度上げること」
- 「最後までやり抜く気合い」が必要
- マーケティングの失敗=リストラ!?
- 商品や結果に対しての責任の度合い
- 手段の多さや自由さ
- お客様に高い価値を提供できるか
- お客様の目的や背景、期待を正しく理解する
- ”クライアントを見る”か”クライアントが目指すものを見る”か
- 自己研鑽ができないとお話にならない
- 学習意欲が高い人が大成する
- エンディング
オープニング
高橋:今回どうしてもゲスト含めて喋りたいなと思ったテーマがあるので、2 人のゲストをまず紹介します。
新庄:株式会社アーラリンクの新庄と申します。誰でもスマホの経営企画部、マーケティングの責任者をやっております。 よろしくお願いします。
川島:株式会社オーリーズ マネージャーの川島と申します。オーリーズは運用型広告を主軸にしながら、マーケティングのご支援をしてる会社になっております。 本日、楽しみにしております。よろしくお願いします。
高橋:まずアーラリンクとオーリーズさんの関係から説明すると、マーケティングのご支援をオーリーズさんにしてもらってます。
オーリーズさんの社長と僕が、同い年で仲良くしてて、 彼もすごい頑張ってるとか、すごい信頼できるということがあったので、オーリーズさんと仕事させてもらっているという関係です。
テーマ「マーケティングの仕事の解像度上げること」
高橋:結構日常や採用シーンとかでちょくちょくイライラする時があるんですが、マーケティングをやりたいっていう人が結構多くて、
なんかマーケティングの仕事って「キラキラしてる」とか「楽しい」とか、「成長できる」ってすごい言われるんですけど、
それに対する、超えなきゃいけない壁とか覚悟みたいなのがあんまり世の中に伝わっていない。
高橋:事業会社としての側面、支援会社としての側面、それぞれマーケティングの仕事って何が違うのかって話をして、解像度を上げていきたい。
そして、これからマーケティングの仕事をしたいっていう人に、この対談を聞いてもらってマーケティングの仕事についての理解を深めてもらえたら、すごくいいんじゃないかなと思ってます。
「最後までやり抜く気合い」が必要
高橋:まず、事業会社であるアーラリンクの新庄さんに聞きたいんですが、アーラリンクのビズデブ(マーケティングや経営企画)において、必要な業務とか必要なスキルってなんだと思いますか?
新庄:ビズデブって事業開発を想起させるものが多いんですけど、 まさにそれと使う筋肉は近いかなと感じています。
新しいものを作るには”0から1”を考える力が必要になるんですが、我々がやっている誰でもスマホのサービスに関しても、ここからさらに伸ばすには何が必要かっていう、” 0ないし1”から新しく考えるような「何か考えて生み出していく」っていうスキルが求められます。
そしてスキルと隣り合わせで「最後までやり抜くみたいな気合い」は必要かなと思ってます。
高橋:やり抜く力は重要だよね。
新庄: めっちゃ大事ですね。 あとはスキルじゃないんですけど、誰でもスマホの商品やお客様のことを徹底的に理解するとか、プロダクトを愛するとか、そこをどれぐらいやりきるかみたいなところが非常に求められると思っています。
まさにビズデブ・事業開発で求められることと一緒かなと思ってます。
マーケティングの失敗=リストラ!?
高橋:顧客のことを思ってやり抜くみたいなね。ここは支援会社さんもすごいありそうな感じがします。
逆に、新庄さんは支援会社と事業会社のマーケティングの違いってどのように感じますか?
新庄:失礼にあたったら大変申し訳ないんですけど、 アーラリンクにおいては営業組織とかがないので、マーケティングが滑ったら従業員の首が飛ぶみたいな(笑)
高橋:(笑)マーケティング滑る、獲得が鈍る、利益売上が損失する、給料上げられない、ないしはリストラしなきゃいけない、っていうところに鬼のように直結してるってことですか?
新庄: そうですね。そこがめちゃくちゃあって、これが感覚として、支援する側と事業を持ってる側の違いではあるかなと感じています。
商品や結果に対しての責任の度合い
高橋:コンサルタントに依頼する側とコンサルタントする側では違うと。ではどんな違いがありそうですか?
新庄:相手に価値を届けるのが仕事なので、やり抜くということは両方とも一緒だと思います。 ただ、実際に結果が出た、出ないによって、何が左右されるかが違うかなと思っています。
高橋:コンサルタントの方は結果が出なくてもコンサルティングフィーはもらえるが、事業会社の方は結果が出なかったらお金がもらえなくなっちゃうので、 すごい苦しいよみたいな感じですかね?
新庄:そうですね。支援会社の視点が見えてないので、”かも”なんですけど、そういう風に感じます。
高橋:責任の度合いが全然違うんじゃないかってことね。
新庄:そうですね。その商品に対する責任の度合いみたいなことですね。
高橋:商品とか、あと結果ね。
新庄:そうですね。
手段の多さや自由さ
高橋:利益を出すとかお客様を増やすっていう手段は、支援会社より事業会社の方が多いと感じるんですが、仕事内容についてはどう思いますか?
新庄:支援会社側だと依頼されたことの範囲でしか動けないという、可動域の狭さみたいなものは感じるかもしれません。
事業会社側からすると、顧客に価値を届けられるんだったら、何をやってもいいじゃないですけど、力の入れ具合や力の入れるところも自分で決められる感じがします。
高橋:なるほど、自由を謳歌するって能力が高くないとできないし、逆に自由が自分を苦しめるみたいなのもあったりする。
そういう側面が事業会社にあるかなと僕は思いますね。一旦ここまでにしておきます。
新庄:ありがとうございます。
お客様に高い価値を提供できるか
高橋: 支援会社さんのマーケティングってどういうこと意識されてますか?
川島:クライアントワークのところでお話させていただくと、やり抜く力も同じく必要ですし、シンプルにお客様に高い価値を提供できる人がバリューの高い人であり、活躍する人だと思ってます。
外部支援業者ですので、良い仕事をして、お客様に満足してもらって、その対価をいただく、これが全ての起点になっています。
高橋:支援会社さんとしては、クライアントの獲得数とか業績とか利益を伸ばせられる人が、マーケーターとして地位を確立していく、会社から評価されるような人になっていくということなんですかね。
川島:おっしゃる通りですね。
お客様の目的や背景、期待を正しく理解する
高橋:どういう人がその価値を提供できる人になってくるんですか?
川島:ここは事業会社と近いところがあるかなと思っていて、オーリーズでバリューに置いている「目的ドリブン」という言葉があるんですけど、
支援する会社様によってミッションが変わってくるので、目的や背景、期待を正しく理解して、その期待の一歩先の付加価値を提供するぞっていう姿勢が非常に重要かなと思ってます。
論理的には正しいけれども、求められないことをやって満足度が上がらないケースも中にはあったりしますので、ちゃんとそこを理解した上で、協働していけるかっていうところが非常に重要かなと思いますね。
高橋:なるほど。つまり、顧客の期待することへの理解と、顧客の事業への理解、どちらもちゃんとしなきゃいけないってことですね。
川島:そうですね。
”クライアントを見る”か”クライアントが目指すものを見る”か
高橋: マーケティング支援会社で活躍できる人とそうじゃない人で、決定的な違いってありますか?
川島:ポータブルスキルだったりとか、ビジネス戦闘力そのものの話だったりとか、スペシャルな専門知識だったり、そういうところはもちろんあるんですけど、
”クライアントを見てるか”と ”クライアントが見てるものを見えているか”が重要だと思っています。
クライアント様を見てしまうと、この人たちにオッケーをもらえるかみたいな発想になってしまうんですが、そうではなくて、クライアント様が目指してるものをちゃんと見て、時にはぶつかり合うことを厭わずに、しっかりと肩を組んでやっていけるかみたいなところが、大きく伸びていくには必要だと考えています。
高橋:いいですね。なんか上司を見て仕事をしてるのか、上司が見てるものを見て仕事をしてるのかというのとなんかすごい近いですね。
自己研鑽ができないとお話にならない
高橋:ちなみに結構、自己研鑽が必要なんじゃないかなと思うんですが、ビジネス戦闘力が高くなる人と高くならない人で、素養とか素質があったりしますか?
川島:そこは間違いなくあります。 特にデジタルマーケティングの世界は日進月歩でテクノロジーとか情報が動いていきますので、毎日、勉強をしなければならない。
私もこの業界に10年以上いますが、5 年前の話なんて今は全く通用しないような状況だったりしますので、 毎日毎日、インプットは欠かさずやってますし、
特に支援会社は専門性とか情報優位性が付加価値になりますので、マストでやっていかなきゃいけないところですね。
もはや議論にすらならないというか、もう当たり前にやらなきゃいけないよねっていう世界。
それがあってかつ、ロジカルシンギングとかクリティカルシンギングなど、いわゆるポータブルスキルを高めていくことによって、
課題解決のスキルを上げていったり、より難易度の高い課題に向き合っていけたりといった動き方になってくるかなと思いますね。
高橋:なるほど、そうですよね。
支援会社さんっていろんな会社のマーケティングをやってるから、マーケティングの視点で切り取った世の中の動向がわかってたり、情報感度が高くて先に勉強してくださってる。
だからこそお願いしてるってのはあると思うんですけど、結局、僕らは僕らでマーケティングとか、通信業っていう商品とか、社会学的な社会の流れとか、日々勉強してくっていうことがやっぱり大事だってことですよね。
学習意欲が高い人が大成する
高橋:会社からというよりは、自分でキャッチアップしてることの方が多いのかなって思っていて、そういうのが好きとか、そういうのができる人がやっぱり残っていくのかなって気がするんですけど、どうですか?
川島:そうですね。 もちろん会社としても情報が集約されるような仕組みがあったりしますけれども、それで全部カバーできるわけでもなかったりしますし、 なので個々人が情報収集だったり勉強するっていうのが素地としてあります。
実際、オーリーズに入社してもらう時に全員ストレングスファインダーっていうものやってもらっていて、成長意欲とか勉強熱心みたいなところが高い割合 で入ったりしますので、結果的にそういう性質を持った人が多いのかなっていうのはありますね。
高橋:ちなみに僕も新庄もストレングスファインダーで学習意欲は1位か2位だった。
川島:私は学習意欲2位か3位でした(笑)
高橋:(笑)我々も学習意欲が高いんじゃないかなって自負してるんですけど。
なるほどね。やっぱり学習意欲が高くてちゃんと勉強するのが楽しいって思えるような人が、うまく成長してるとか大成してるってことなんですね。
川島:はい、そうですね。
エンディング
高橋:全然序章で、聞きたいことがたくさんあるんですけど、ここら辺で切っておかないと、むちゃくちゃ長くなっちゃうと思うんで、一旦この辺で切っておきます。ありがとうございました!
川島・新庄:ありがとうございました!
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。