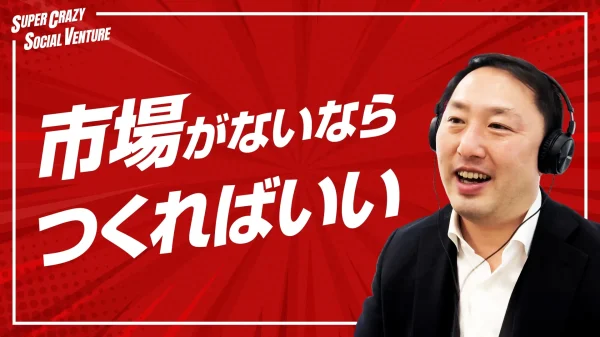#32 ”おままごと”化したインターンシップへの違和感
「学生も企業側も、これ何のためにやってんだっけ?ってなるんですよ」
──従来の“おままごと”化したインターンへの違和感。アーラリンクが設計したのは、徹底的に顧客の声に向き合いながら、新事業や新サービスを立案するというもの。
資料作りで終わらない、リアルな顧客との接点が、参加者に“ガチさ”と“理念共感”を呼び起こしていきます。
- 目次
- インターンシップ始動
- 提案書だけじゃ、意味がない
- お客様の課題からスタートする
- 社員と一緒に、事業を練り上げる
- AIを活用してリアルな成果物
- 批判思考で深める2日目
- 最後はプレゼンとリアルな評価
- “おままごと”からの脱却
- 「生の声」が動機をつくる
- 9月・10月に“緊急開催”も視野に
- 懇親会で“会社の中身”に触れる
- “偶然の副産物”が生んだ大きなメリット
インターンシップ始動
インターンシップを7月24日から1回目をやって、夏の間に5〜6回やる予定です。27卒の新卒採用に関しては、このインターンで学生との接点を終えちゃう可能性すらあるぐらい超早期選考になっています。
インターン2日間のパフォーマンスが良ければ、そのまま最終面接に近い流れになって、9月か10月には内定出すっていうスケジュール感なんです。
提案書だけじゃ、意味がない
アーラリンクでも以前にやっていましたが、よくある新規事業立案とか新サービス立案系のインターンシップって、ガチさがなくて「おままごと」っぽいんですよね。
最後のアウトプットを紙の提案書を使って、グループで発表して「良かったね」で終わる。さらに、学生が社員に向けてプレゼンしている構図自体が「おままごと」っぽくしているんじゃないかなと。
そこで実際のお客さんに登場してもらうっていう決断をしました。
お客様の課題からスタートする
初日にインターンやアーラリンクの説明をしてから、お客様の課題をヒアリングして、それをもとに新規事業や新サービスを考えるっていう流れにしたんです。
まずはお客さんへの理解が必要になってきますよね。顧客の課題を聞き出す能力がいきなり求められるわけです。
「この人のこの悩みを解決したい」っていう切実さから事業を組み立てる。ヒアリングで浅い質問をすれば、浅い答えしか返ってこない。だからこそ、ちゃんと深く聞く力が必要で、それをその場で身につけてもらうんです。
お客さんに直接質問して、応えてもらうその経験こそが、「おままごと」感を払拭して、ぐっとくる感じになります。お客さんにも思ったことをそのまま答えてくださいと伝えています。
社員と一緒に、事業を練り上げる
午前中にヒアリングをして午後からは事業を練る。1時間くらい考えて、僕のところに持ってきてもらって、フィードバックをして、また考えてもらう。これを5〜6回繰り返します。
僕が普段、新規事業を考える時の思考プロセスをそのままワークシートに落とし込んでるので、めちゃくちゃ細かく考えてもらうんです。
たとえば「顧客の痛みとかかゆみにちゃんと届くサービスなのか」「既存市場の状況」「差別化ができているのか」「PRの方法」「サービスの値段」「配送方法」とか。
ワークシートの補助力とフィードバックによる思考の整理、社員の徹底フォローで、限りある時間の中でやり切ります。
AIを活用してリアルな成果物
2日目はもっと実践的です。まずAIの使い方をレクチャーして、そこから実際にWebサイトやアプリのUIを作ってもらう。これも「おままごと」を排除するためです。
紙で書いた資料よりも、実際に見えるモノをつくる方が圧倒的にリアリティがありますからね。今ってAIがアシストしてくれるので、大学3年生でも本当にそれっぽいものが作れるんですよ。
批判思考で深める2日目
さらに1日目の楽観的な思考から一転して、批判的な視点で事業を見つめ直してもらいます。「この事業がうまくいかないとしたらなぜなのか?」っていう問いを徹底的に投げかけるんです。
僕もかなり鋭いフィードバックをしますし、それをもとに参加者自身が「本当にこれでいけるのか?」って自問自答する時間にしてもらいます。
最後はプレゼンとリアルな評価
午後には、また別のお客さんに来てもらって、実際に自分たちが考えた事業を20〜30分かけてプレゼンします。評価するのはそのお客さんたち。0点から10点までのスコアをつけてもらって、さらに僕からも社長評価として得点をつけて、合計点で勝敗が決まるというスタイルです。
お客さんから一次情報を聞いた上で事業を作ることが一番大切で、僕自身が新規事業を作るときの流れを学生にも体験してもらっています。
“おままごと”からの脱却
よくあるインターンって、学生も企業側も「何のためにやってるんだっけ?」ってなることがあるじゃないですか。
でもお客さんの本音に触れて、それに対して本気で答える。さらにAIを駆使してHPを作って具体的にアウトプットをする。このリアルさがガチで取り組む空気を作るんですよね。学生も自分ごととして本気で取り組んでくれるんです。
「生の声」が動機をつくる
紙の資料みたいな手触り感のない情報じゃなくて、お客さんの“生の声”から事業をつくると、リアリティが出るんですよね。
最終的に「お金を払いたいかどうか」をお客さんに判断してもらうので、適当なものは出せない。初日のヒアリングでそれが伝わるから、自然と「ちゃんとしなきゃ」っていう動機が生まれるんです。お客さんの質問も鋭くて、そこがまた面白いんですよ。
9月・10月に“緊急開催”も視野に
7月、8月の回に参加してくれた学生の反応がすごく良ければ、9月や10月に“緊急開催”もありえると思ってます。「ガチな感じが良かった」と口コミで広まって、「私も出たい」って人が集まってくるのが一番理想なんですよね。
だから、ラジオを聴いて面白そうだなって思った人は、ぜひ気軽に参加してほしいなと思ってます。
懇親会で“会社の中身”に触れる
2日目が終わったあと、夜に会社で懇親会をやります。社員たちも各チームにがっつり張りついてサポートしてくれてるんですけど、その場で改めてフィードバックをしてもらったり、アーラリンクで働くってどんな感じなんですか?みたいな質問をしてもらったり。僕も当然そこにいるので気軽に話したりして。
“偶然の副産物”が生んだ大きなメリット
今回のインターンで気づいたことのひとつが、採用過程の中で「参加者にお客さんを見てもらうこと」がめちゃくちゃ効果的だったってことです。
僕らが会社の良さを語るよりも、リアルなお客さんが「アーラリンクにこんな期待してます」とか「こんな課題があります」って言ってくれることの方が100倍伝わる。
これは狙ってたわけじゃなくて偶然の副産物でした。BtoCの会社だったら、こういう「お客さんを見せる」っていう採用活動は有効なんじゃないかなと思ってます。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。