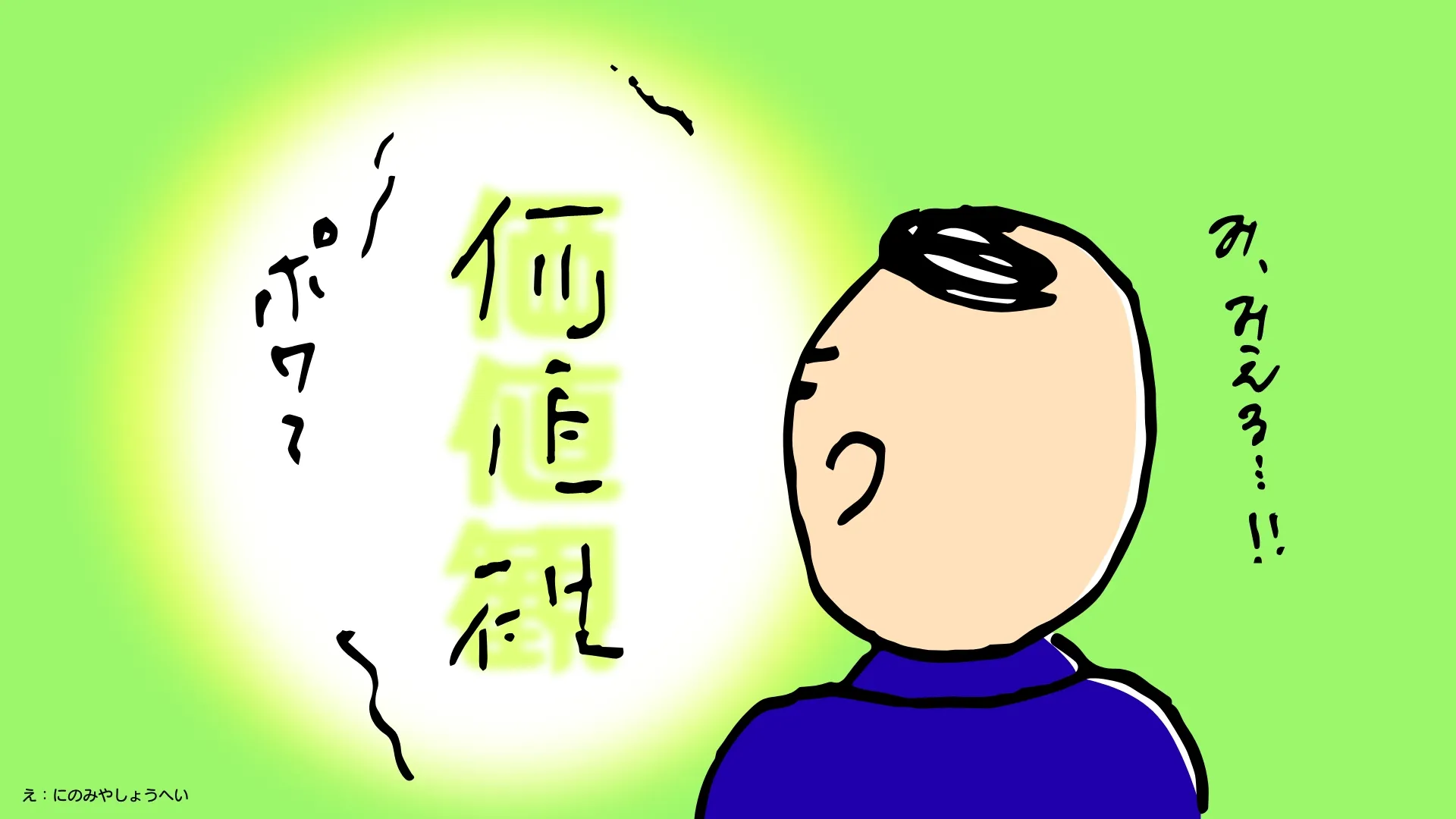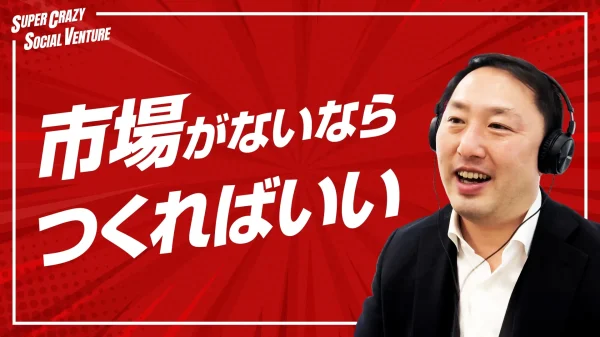アンバサダー編|価値観の可視化が文化を育てる
「言葉を見えるようにして使っていくことがとても大事だなって思っています」
3部構成のアンバサダー編の最終回です。
価値観を明文化し、日常的に使える言葉にしておくことで、組織内のコミュニケーションの質が変わります。
社員一人ひとりが同じ土台を持ち、判断や行動の背景に一貫性が生まれることで、信頼と連携が自然に育ちます。
その結果、業務が単なる作業から「意味のある仕事」へと変わっていきます。
- 目次
- 価値観を言語化し浸透
- アンバサダー活動の手応え
- 日報文化との連動で内省を促進
- 共通言語が判断軸になる
- 自己律の芽生え
- 調和の行き過ぎに歯止め
- 透明性のある仕組みづくり
- 禁止ルールは浸透が早い
- 柔軟な価値観浸透戦略
- 小規模対話で深掘り促進
- 上司・部下を越えた対話
- 日常の行動に一貫性が生まれる
- 言葉が文化と未来をつくる
価値観を言語化し浸透
僕はこれまで、会社の価値観の言語化と浸透に力を入れていきました。
今では“アンバサダー”という社員たちが、自分の言葉で価値観を語り、社内に広めてくれています。
全24項目の行動規範をもとに、それぞれの解釈や実践例を交えて話すことで、聞く側も理解を深めやすくなっています。
こうした取り組みのおかげで、全社的に価値観が少しずつ浸透してきているという実感があります。
アンバサダー活動の手応え
最近では、アンバサダーの話を聞いた社員から「他の人の考え方を知ることで、自分の仕事にも新たな視点が加わった」という声が届くようになりました。
社員が自らの体験を交えて価値観を語ることで、共感が広がり、組織全体の“思想の解像度”が上がってきていると感じています。
これは、これまで僕が取り組んできた価値観の浸透活動の成果の一つだと捉えています。
日報文化との連動で内省を促進
うちの会社にはもともと日報を書く文化がありますが、価値観の共有と組み合わせることで、より大きな効果が生まれています。
社員が日報の中で「今日の行動はどの価値観と結びついていたか」「どんな改善ができるか」を自然と振り返るようになり、価値観が実際の業務や判断の軸として生きるようになっていきました。ここでも「言葉を見えるようにして使うこと」の力を強く感じています。
共通言語が判断軸になる
価値観が言語化されていると、日々のマネジメントでもとても有効に機能します。
たとえば会議の時間を守る場面で「会社の行動規範に『時間を守る』と書かれている」と伝えることで、個人の意見ではなく組織としての価値観になります。
そうすると伝える側の心理的負担も減り、指摘もしやすくなるんです。
共通言語があることで、社員間のやり取りも建設的でスムーズになります。
自己律の芽生え
価値観が浸透してくると、社員の中に「自分もそれを守らなければ」という意識が芽生えてきます。
たとえば「時間を守ろう」と他者に伝えた社員が、自分が守れていなければ意味がないと感じるようになる。
このような“価値観に対する責任感”が、自律的な行動につながっています。
ただルールを示すだけでは得られない、価値観を内面化する文化が育ちつつあるのを実感しています。
調和の行き過ぎに歯止め
アーラリンクは調和を大切にする文化を持つ組織です。
でも、空気を読みすぎることで意見を言いづらくなる「行き過ぎた調和」が起きるリスクもあります。
僕はそれを防ぐためにも、価値観を明文化し「言葉を見えるようにして使っていくこと」がすごく大事だと思っています。
組織としての共通認識があれば、配慮しつつも必要な発言や行動がしやすくなると感じています。
透明性のある仕組みづくり
僕は組織内の透明性を大切にしています。判断や情報共有が裏で進むことを防ぎ、責任の所在を明確にするためです。
また、投票やフィードバックも原則「記名式」調和の文化が強い組織だからこそ、健全な対話とオープンなコミュニケーションを保つ工夫が必要だと思っています。
禁止ルールは浸透が早い
価値観を広めるうえで「こうしよう」より「こうしてはいけない」という禁止ルールのほうが浸透が早いと僕は考えています。
これは宗教の教えにも通じます。仏教で言えば「殺してはいけない」「嘘をついてはいけない」など、禁止事項は明快で記憶に残りやすい。
特に業務に短時間しか関われないアルバイトや派遣スタッフには、まず禁止ベースで伝えるほうが効果的です。
柔軟な価値観浸透戦略
社員には前向きな価値観を対話で伝える。
一方で、時間が限られるアルバイトや派遣スタッフには、まず「やってはいけないこと」を明示する。これはリーダーシップ理論にも通じます。
「どうあるべきか」と「何をしてはいけないか」の両方が必要であり、相手の状況に応じて戦略を使い分けることが、価値観を現場に浸透させるうえで不可欠だと僕は考えています。
小規模対話で深掘り促進
価値観を理解するだけでなく、少人数での対話によって深く考えることが大切です。
僕は5人程度の対話の場を設け「顧客創造活動を大切に」といった項目をもとに議論するようにしています。
現場での具体的な悩みや判断にどう結びつけるかを話し合うことで、社員一人ひとりが価値観を自分ごととして捉えるようになります。
こうした対話が文化としての価値観を根付かせる鍵になると考えています。
上司・部下を越えた対話
価値観を共有する取り組みは、役職や年齢を超えた意見交換のきっかけにもなっています。
最近では、部下から「その行動は会社の価値観に反していませんか?」という指摘が自然に出るようになり、上司も「自分の行動を見直すきっかけになった」と話してくれます。
こうした対話が日常的に行われることで、よりフラットで健全なコミュニケーションの土壌が育まれてきていると感じています。
日常の行動に一貫性が生まれる
価値観を明文化し、日常的に使える言葉にしておくことで、組織内のコミュニケーションの質が変わります。
社員一人ひとりが同じ土台を持ち、判断や行動の背景に一貫性が生まれることで、信頼と連携が自然に育ちます。
その結果、業務が単なる作業から「意味のある仕事」へと変わっていきます。
だからこそ僕は、言葉を見えるようにして使っていくことがとても大事だなと思っています。
言葉が文化と未来をつくる
ここまで3週にわたって、アンバサダー選挙や価値観の浸透活動について話してきました。
抽象的な理論から、社員の具体的な声、実際の取り組みや変化まで幅広く共有できたと思っています。
僕たちはこれからも「文化としての価値観」を社員全員で育てていきたい。
そのために「言葉の力で文化はつくられる」という信念のもと、言葉を見える形で使っていく姿勢を大切にしていきます。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。