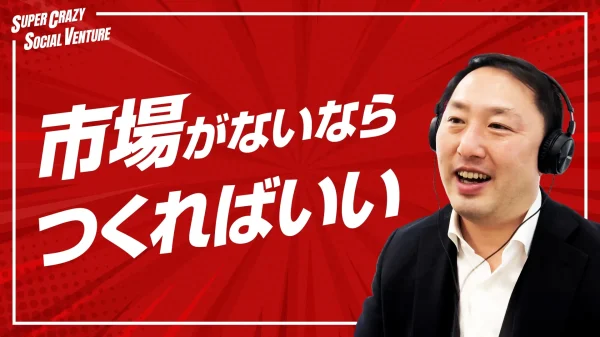志が仕事に意味と推進力を与える
「”やらなきゃ”が”やりたい”に変わる」
自分の中にある志と、会社が掲げているミッション。この二つが重なったとき、仕事の意味が大きく変わります。「こなす業務」ではなく「自分がやりたいこと」に変わる感覚が出てくる。そのスイッチが入るだけで、日々のパフォーマンスやモチベーションも大きく変わると思います。
- 目次
- 小さな志から自分を見つめ直す
- 志は、気づけばすでにある
- 志が仕事に意味と力を与える
- 志は過去の経験から見えてくる
- 志と価値観が重なる場所を見つける
- 対話が気づきを引き出す
- 意図的に立ち止まり、再確認する
- 過去から未来の選択をつくる
- 志を共有することが、チームの関係性を深める
- 志と組織の未来を重ねる
小さな志から自分を見つめ直す
自社スタッフやこれから入る方にも聞いてもらうと、すごくいい話かもしれないと思ったので、最近行ったワークショップの話をします。その話の中で、特に印象に残ったのが「小さな志から考える」という視点です。
たとえば私自身、膝コロ(腹筋ローラー)を毎日継続しています。
最初は30回から始め、週ごとに回数を1回ずつ増やして現在は45回です。筋肉痛の日も含めて15週以上続けています。これは誰かに指示されたものではなく、自分で決めた日課です。
このような行動は一見小さく見えますが「今日もやり切った」という感覚が、日々の自信や自己肯定感につながっており、結果的に自分自身の行動の軸を形作っていると感じます。
こうした積み重ねが、自分の中にある価値観を再認識する手がかりになっている実感があります。
志は、気づけばすでにある
「自分には志がない」と感じている人は少なくありません。しかし実際は、“気づいていない”だけというケースがほとんどだと思います。
志というと、特別な使命や壮大な目標のように捉えられがちですが、実はもっと身近なところにあります。
たとえば「人の役に立ちたい」「目の前の仕事をより良くしたい」といった日常的な思いも、立派な志です。
今回のワークでも「これも志なんですね」と気づく場面が多くありました。
「志はあるが“気づいてない”が多い」という言葉は非常に的を射ていて、日常の小さな動機や思いに目を向けることが、志を発見する第一歩になると実感しました。
志が仕事に意味と力を与える
業務に追われる日々の中では、仕事を「こなすもの」と捉えてしまうこともあります。
とくにリーダー層のように多くのタスクと責任を抱える立場では「なぜこの仕事をしているのか」という問いを見失いがちです。
ただ、自分の中にある志と目の前の業務が重なった瞬間「やらなきゃ」が「やりたい」に変わる感覚が生まれます。この変化は非常に大きく、同じ仕事であっても、そこに感じる意味やエネルギーがまったく異なるものになります。
「志が仕事に意味と力を与える」という実感は、今回のワークを通じて多くのメンバーが共有できた気づきでした。
志は過去の経験から見えてくる
志は突然現れるものではなく、自分の過去を丁寧に振り返る中で見えてくるものです。今回実施した「自分の過去を振り返る4ステップ」は、そのための有効なプロセスでした。
① 小さな志を確認する
② 真剣に取り組んだ経験を掘り下げる
③ 原体験や価値観を言語化する
④ 志と会社のミッションの接点を考える
僕自身、高校受験を通じて得た「努力すれば結果が出る」という感覚が、今の意思決定にもつながっています。過去の経験を見つめ直すことで、自分が大切にしていることに気づき、それが将来の選択肢を広げる判断材料になると感じています。
志と価値観が重なる場所を見つける
企業には様々な側面があります。組織文化、チーム、人、事業、社会的意義など。
どの要素に自分の価値観が重なるかによって、働き方に意味を見出せるポイントは変わります。
たとえば「仲間と協働すること」が大事だと思っている人にとっては、誰と働くかが重要ですし「社会に与えるインパクト」に意義を感じる人にとっては、事業の方向性が軸になります。
「価値観と仕事の接点を見つける」という視点を持つことで、会社の中での自分の意味づけが変わり、同じ業務でも感じ方やエネルギーの出し方が変わってくる。
それが、今回のワークでの重要な学びの一つでした。
対話が気づきを引き出す
志を見つけるには、単に紙に書き出すだけではなく人との対話がとても重要です。今回のワークでは、4人で事前に準備したワークシートをもとに、約5時間かけて相互に共有し合いました。
形式的なプレゼンではなく、相手の話を深掘りするような質問を交えた対話を行うことで、自分では見えていなかった価値観や志に自然と気づくことができました。対話のプロセスそのものが、自分自身を整理し、他者を理解する手段になったと感じています。
意図的に立ち止まり、再確認する
日常の業務に追われる中では「志を考える時間」はどうしても後回しになりがちです。
しかし、意図的に立ち止まって自分と向き合う時間を取ることが、非常に大きな意味を持つと感じました。
今回のようなワークを年に1度は設けたいと思いますし、可能であれば日常を離れた場所——たとえば自然の中で1日かけて実施することができれば、さらに深い気づきが得られるはずです。
業務の延長ではなく「自分を見直す時間」そのものを組織として設計していく必要性を強く感じました。
過去から未来の選択をつくる
高校受験に本気で取り組んだ経験が、今の自分の意思決定の軸になっていると改めて感じています。
「努力すれば結果が出る」「自分の選択には納得したい」という価値観は、あの経験からきています。
このように、自分の原体験を丁寧に振り返ることは、現在の判断基準や未来の意思決定の精度を高めることにつながると実感しました。「自分の過去を振り返る4ステップ」を通じて、人生の文脈を再確認し、自分なりの選択基準を持てるようになること。それが志の可視化につながっていると感じています。
志を共有することが、チームの関係性を深める
今回のワークでは、志を言語化するだけでなく、それをチームで共有することによって得られる効果も非常に大きかったです。
お互いの価値観や過去の経験を知ることで、相手への理解が深まり「その人らしさ」や「こだわり」が見えるようになりました。
これにより、チーム内での信頼や対話の質も高まり、結果的に「志が仕事に意味と力を与える」という感覚がチーム全体に広がったと感じています。
志と組織の未来を重ねる
こうしたワークを通じて得られる気づきは、単なる個人の内省にとどまりません。志が明確になることで、その人がチームや組織においてどのような役割を担いたいか、どこで力を発揮したいかが見えてきます。
それは結果的に、適材適所の配置や抜擢の判断、チームビルディングにおいても大きな示唆になります。
個人の志と組織のビジョンが重なることで、持続的なエンゲージメントが生まれる。このような機会を、今後も継続的に設けていくことが、組織の成長にとって必要だと感じています。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。