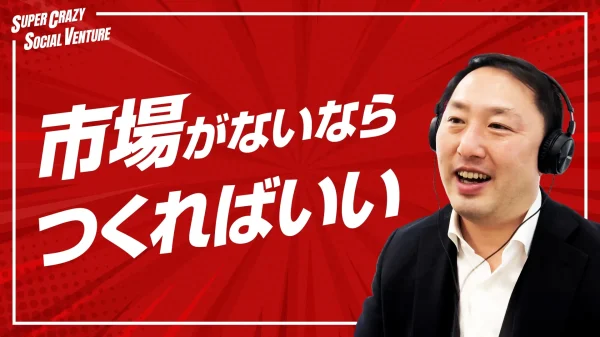#41 ソーシャルビジネスは「選ばれる」ではなく、対等な関係のビジネスである
利益を削ることでも、恩着せがましい支援でもなく、純粋にお客様が欲しいものを提供し続けること。お客様と企業の関係を“対等”に捉えることで見えてきた新しい経営の形を、自らの体験と共に語ります。
- 目次
- 学生インターンに感じた「本気スイッチ」の変化
- 採用の早期化と内定承諾の課題
- 資本主義とソーシャルビジネスの関係性
- 「助ける側」と「助けられる側」を超える発想
- ビジネスにおける対等さの魅力
- 貧困層との関りで抱いた葛藤と気づき
- 価格設定とお客様の選択の自由
- 利益を守ることが社員と顧客を守る
- ソーシャルビジネスにおける本当の価値提供
学生インターンに感じた「本気スイッチ」の変化
直前まで大学生のインターンシップをやっていたんですけど、9月の終わりに入るこの時期って就活生にとって潮の変わり目なんでしょうね。
夏のインターンは遊園理感覚で参加していたのかもしれないけど、今回は全員スーツで遅刻無し。たった2週間でこんなに変わるのかと驚きました。
学生には「夏から本気でやった方がいいよ」と伝えたいです。企業は超見てますからね。
採用の早期化と内定承諾の課題
就活はどんどん早くなっています。今年は9月後半で変化を感じましたが、来年はもっと早まるかもしれない。
ただ、内定を早く出しても承諾がずっと来ないケースも多く、最終的に別の会社にいかれてしまう。
だからうちは承諾機嫌を設けることにしました。ずるずるするより「来ないなら終わり」とカウントする方が健全だと思っています。
資本主義とソーシャルビジネスの関係性
国の補助で成り立つ事業、例えば保育園や医療はどうしても対等感が薄れる。
でもお金を直接払うビジネスは、個人の尊厳を守れる仕組みだと思うんです。
お客様と企業が「対等」でいられることが、ビジネスの一番の魅力じゃないでしょうか。
「助ける側」と「助けられる側」を超える発想
僕らのお客様は通信に困っている人が多いけれど、「助けてあげている」という意識はありません。
むしろ「選んでいただいてありがとうございます」という気持ちです。
こちらが変なことをすればお客様は離れるし、だからこそ真剣にサービスを提供できる。
ビジネスは相手の尊厳を傷つけない関係だと感じています。
ビジネスにおける対等さの魅力
国の補助で成り立つ事業、例えば保育園や医療はどうしても対等感が薄れる。
でもお金を直接払うビジネスは、個人の尊厳を守れる仕組みだと思うんです。
お客様と企業が「対等」でいられることが、ビジネスの一番の魅力じゃないでしょうか。
貧困層との関りで抱いた葛藤と気づき
僕自身、お金がない時期が長かったんです。インターネットも携帯も止まる、家賃の催促も来る。
そんな生活をしていたからこそ「財布事情が苦しいお客様からお金をもらうのはどうなんだろう」と悩んでいました。
でも実際は、最安プランばかり選ばれるわけじゃない。ギガが多いプランや保証が充実したプランを選ぶお客様も多い。
つまり、お金がないから助けるという発想自体が余計だったんだと気づきました。
価格設定とお客様の選択の自由
大事なのは選択肢を用意すること。安いプランも高いプランもあって、その中からお客様が自分の意思で選べばいい。
それが対等な関係だし、僕らは純粋に「いいと思うもの」を出すことに集中すればいいんです。
利益を守ることが社員と顧客を守る
安くしすぎて利益を削ると、今度は社員が疲弊します。結果的にサービスの質が落ちてしまう。
それでは対等な関係は成り立たない。だから僕らは必要な利益をいただき、その上でお客様に選んでもらう。そのシンプルさが大事だと思います。
ソーシャルビジネスにおける本当の価値提供
お客様を二番手に置いた「会社のために良いことをしよう」という発想では続かない。
やっぱりお客様が欲しいものを純粋に提供することが一番重要です。
助けてあげているのではなく、対等な関係の中で価値を届ける。それがソーシャルベンチャーとして働く意味であり、僕自身が強く感じた気づきでした。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。