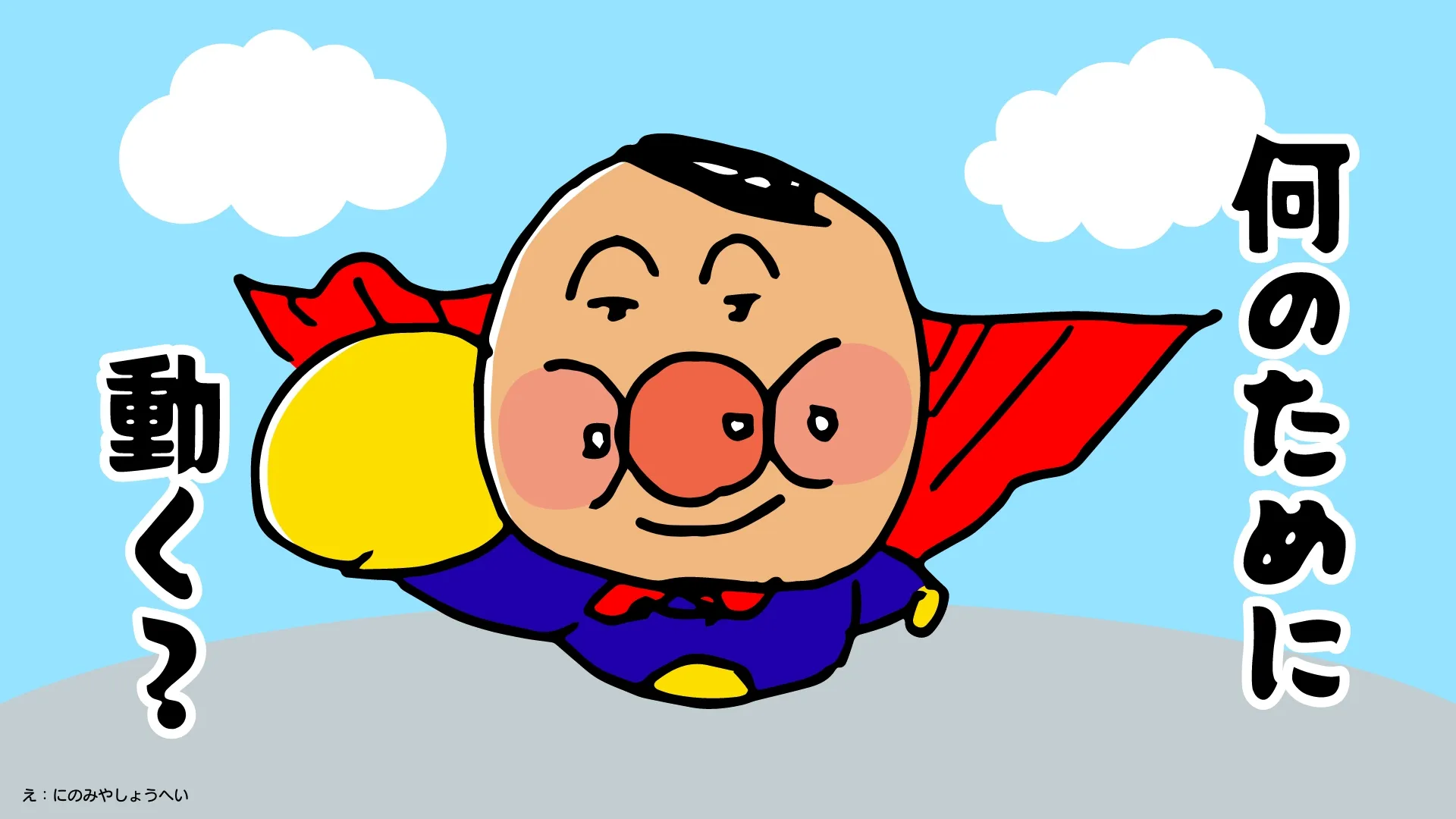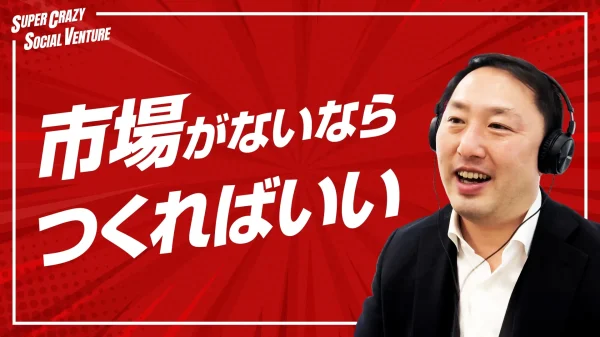アンバサダー編|リーダーに求められる資質とは
「リーダーには個人と組織の融合が必要」
前回に続き、アンバサダー編の第2部です。誰かに頼られることが目的ではなく、自分が何のために動くのかを大事にしたい。
リーダーとは、自分の欲と組織の理想が重なる場所を探し続ける存在なのかもしれません。
成長欲求と貢献意識、権限の使い方、肩書きの目的化の危うさなど、リーダーシップをめぐるリアルな葛藤と学びを通じて“信頼される人”ではなく“信頼できる人”が担うべき役割についてを話します。
- 目次
- リーダーシップを語り続けた5日間
- コーチング型リーダーの重要性
- 組織成果と個人欲求の両立
- 権限の正しい使い方が鍵
- 組織人格者が担うべきリーダー職
- 組織人格と私欲の矛盾について
- 良いリーダーの動機とは?
- 成長欲求と貢献意識の融合
- 肩書きが目的化する危うさ
- 欲求の根源を見る重要性
- 若者のリーダー離れとその背景
- 理念に共感する人が導く組織
- トライアンドエラーの組織運営
- 組織づくりに終わりはない
リーダーシップを語り続けた5日間
今回も、前回に引き続き「リーダーシップ」についての話をしていきます。
特に今回は、アーラリンクで行っている「アンバサダー総選挙」という取り組みを入り口にして「リーダーとは何か」というテーマを深掘りしていきたいと思っています。
僕自身、今ちょうど朝礼という形で5日間くらいかけてずっと「リーダー」について語っていて、その中で感じていることを整理しながらお話ししていきます。
コーチング型リーダーの重要性
前回もお話ししましたが、リーダーにはトップダウン型、ビジョナリー型、ベースセッター型、コーチング型など様々なスタイルがあります。
僕自身はトップダウン型やビジョナリー型は得意ですが、コーチング型はこれまであまり得意ではありませんでした。ですが今は意識的に学んでいて「今日はとにかく聴く」と決めたら徹底して人の話を聴くようにしています。
リーダーシップは場面に応じて型を使い分ける柔軟さが必要だと感じています。
組織成果と個人欲求の両立
会社が存続するためには2つの条件があります。1つは組織として成果が出ていること。
もう1つは個人の欲求が満たされていることです。
お給料をもらう、共感できる仕事をする、成長できるなど、社員の欲求は多様です。
リーダーには、この両方に貢献する責任があると僕は思っています。
組織成果と個人の満足が同時に満たされる環境をどう作るかが、リーダーに問われていると思っています。
権限の正しい使い方が鍵
リーダーは、与えられた権限を組織のために正しく使わなければいけません。
個人の承認欲求や支配欲を満たすために使ってしまうと、組織は一気に崩れていきます。
たとえば、トランプ大統領のように「自分の欲のために暴走するんじゃないか」と不安視されるような状態。
僕は、そういった“個人主義者的な傾向”を持つ人には、組織としてリーダーのポジションは任せられないと考えています。
組織人格者が担うべきリーダー職
リーダーに任せられる人というのは、“組織人格”を持っている人だと思います。
利他的な視点を持ち、組織や仲間に自然と貢献したいと思える人。そういう人であれば、責任や権限を安心して任せることができるんですよね。
逆に、自分の名誉や地位のためだけに動くような人には、いくら優秀でもリーダーは任せたくない。組織の未来を託せる人に任せたいというのが僕の基本的な考えです。
組織人格と私欲の矛盾について
会社が存続するには「個人の欲求が満たされること」が必要です。でも一方で、リーダーに求めるのは“私欲を抑えられること”。
つまり、欲求が必要だけど欲を出しすぎるとリーダーには向かないという矛盾が生まれます。そこで重要なのが「個人の欲と組織の利益が一致しているかどうか」です。
たとえば「人を育てたい」「大きな仕事を成し遂げたい」という欲は、組織にとってもプラスなんですよね。
良いリーダーの動機とは?
「人の成長に関わりたい」「大きな仕事を成し遂げたい」「自分自身が成長したい」などの欲求は、個人の資質であると同時に、組織の成長にも繋がる動機です。
僕自身も「大きなことを成し遂げたいからこそチームで動く」という想いを持っています。
成長したいという気持ちは、リーダーの強いモチベーションになりますし、その先に社会や組織への貢献があるなら、とても良い形だと思います。
成長欲求と貢献意識の融合
「成長したい」という気持ちは、自己実現の途中段階にある健全な欲求です。
そして本当に成長した人は、やがて社会や組織に貢献したいという想いを自然に持つようになります。
僕の周囲にも、成長を経て「次は周りのために何かしたい」と思う人がたくさんいます。
だから成長欲求を持つことは悪いことじゃなくて、むしろリーダーにふさわしい姿勢だと考えています。
肩書きが目的化する危うさ
リーダーという肩書きがゴールになってしまうと、本質的な目的を見失ってしまいます。「社長になりたい」という人はいますが、それが“承認されたいから”だった場合、うまくいかなくなる可能性が高いです。
プライドだけ残って中身が伴わない状態になる。リーダーは肩書きではなく、何を成し遂げたいのか、どんな組織にしたいのかという目的が明確であることが必要です。
欲求の根源を見る重要性
僕は人を見るときに、その人の“根源的な欲求”を見ようと意識しています。
なぜその人はリーダーになりたいのか?何のために頑張っているのか?表面的な言葉ではなく、深層にある本音に目を向けています。
本人も気づいていない動機が、組織にどう影響するかを考えることがとても重要だと思っていて、リーダー選定においては常にそこを見ようとしています。
若者のリーダー離れとその背景
最近は「リーダーになりたい」と自ら言う若手が少なくなっています。
役職を押し付けられる、やらされてる感があると感じている人が多い傾向にあります。
でも、そういう人がダメというわけではありません。むしろ時代の変化として普通のこと。だからこそ改めて「リーダーって何か?」を考え直すタイミングなんじゃないかなと思っています。
理念に共感する人が導く組織
「人を育てたい」「会社をよくしたい」「いいサービスをつくりたい」という動機は、理念への共感から生まれます。
こういう人がリーダーになると、組織全体の方向性が整っていく。
僕自身も、そういう想いで会社をやっているし、そういう動機を持つ人にこそ、組織を引っ張ってもらいたい。
理念に共感できるかどうかは、リーダーにとって非常に大事な資質だと思います。
トライアンドエラーの組織運営
人を見る目って本当に難しい。だから僕は社員に「間違ってもいい」と伝えています。
大切なのは、その失敗から何を学んだかということ。僕自身もたくさんの失敗をしてきたし、そこから見えてきたことが今に繋がっています。
リーダーを育てるにも、任せてみて失敗させてみて、そこから育っていくことが多いと思っています。
組織づくりに終わりはない
組織づくりって、終わりがないんですよね。自分自身も成長するにつれて、人の見方が変わったり、相手の可能性を引き出せるようになったりしてきた。
だから組織って、常に変化と成長を続けていくものだと思います。
今も僕自身、挑戦中で、完璧なんて到底言えない。でも、その未完成さこそが、組織の可能性であり、面白さだとも思っています。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。